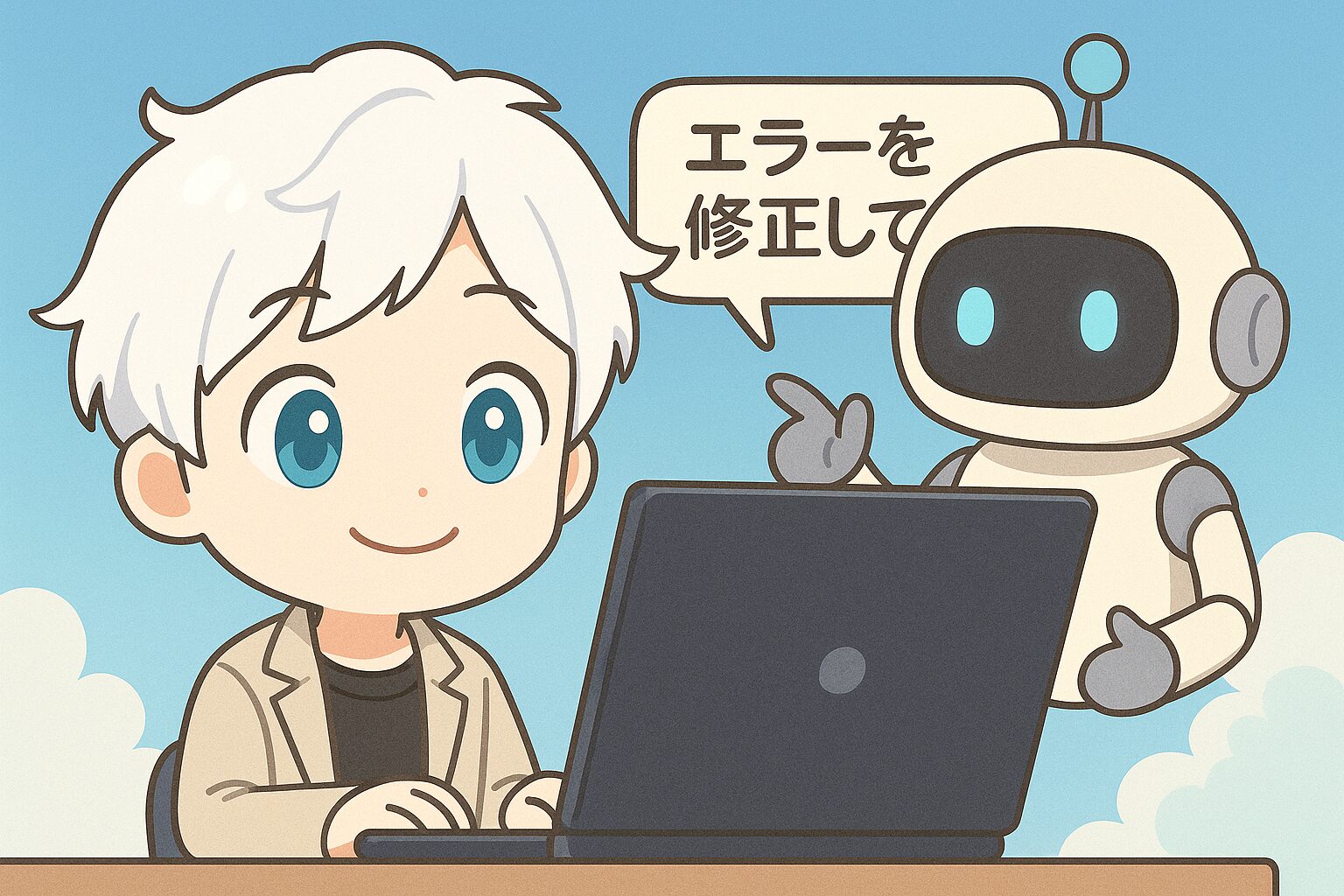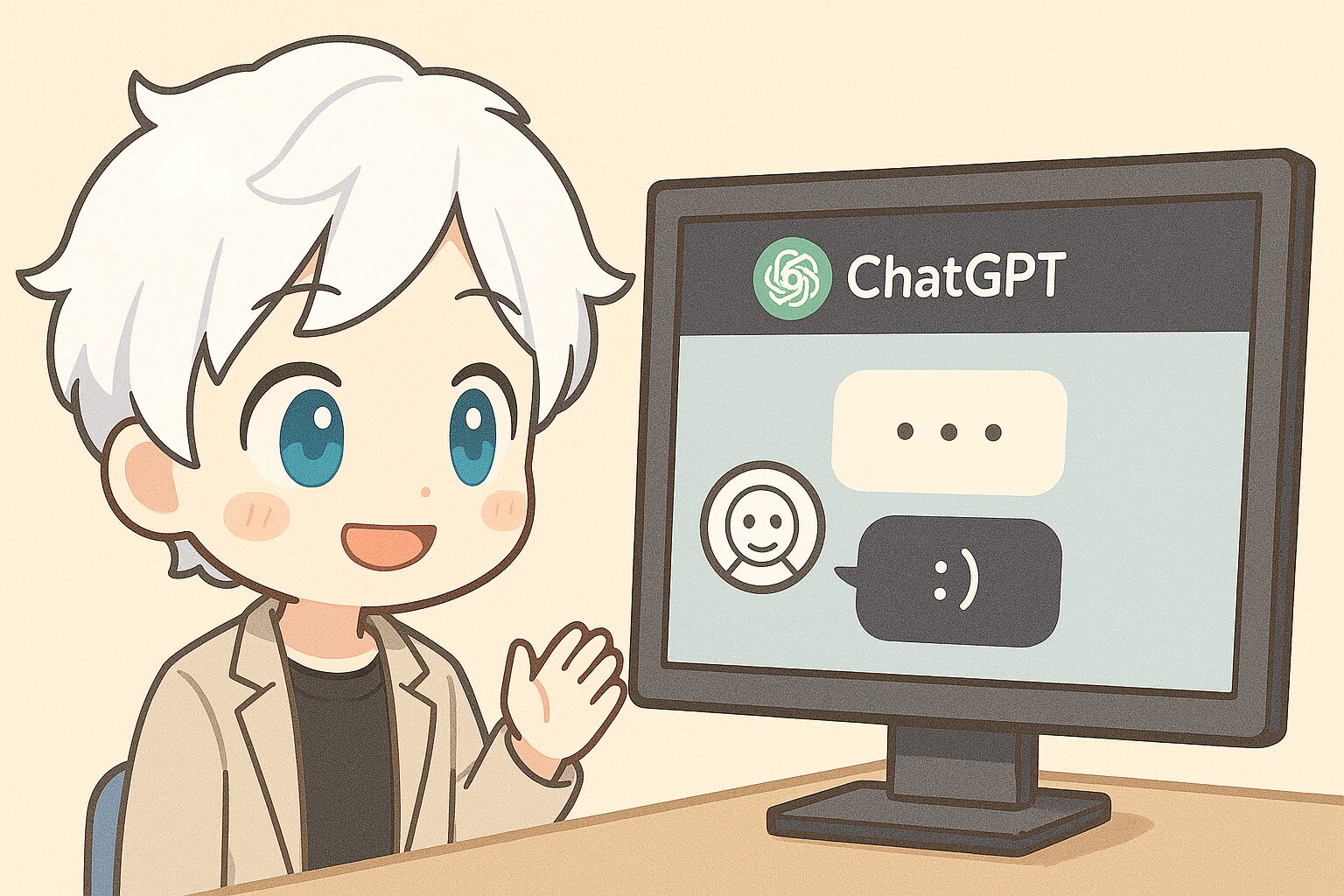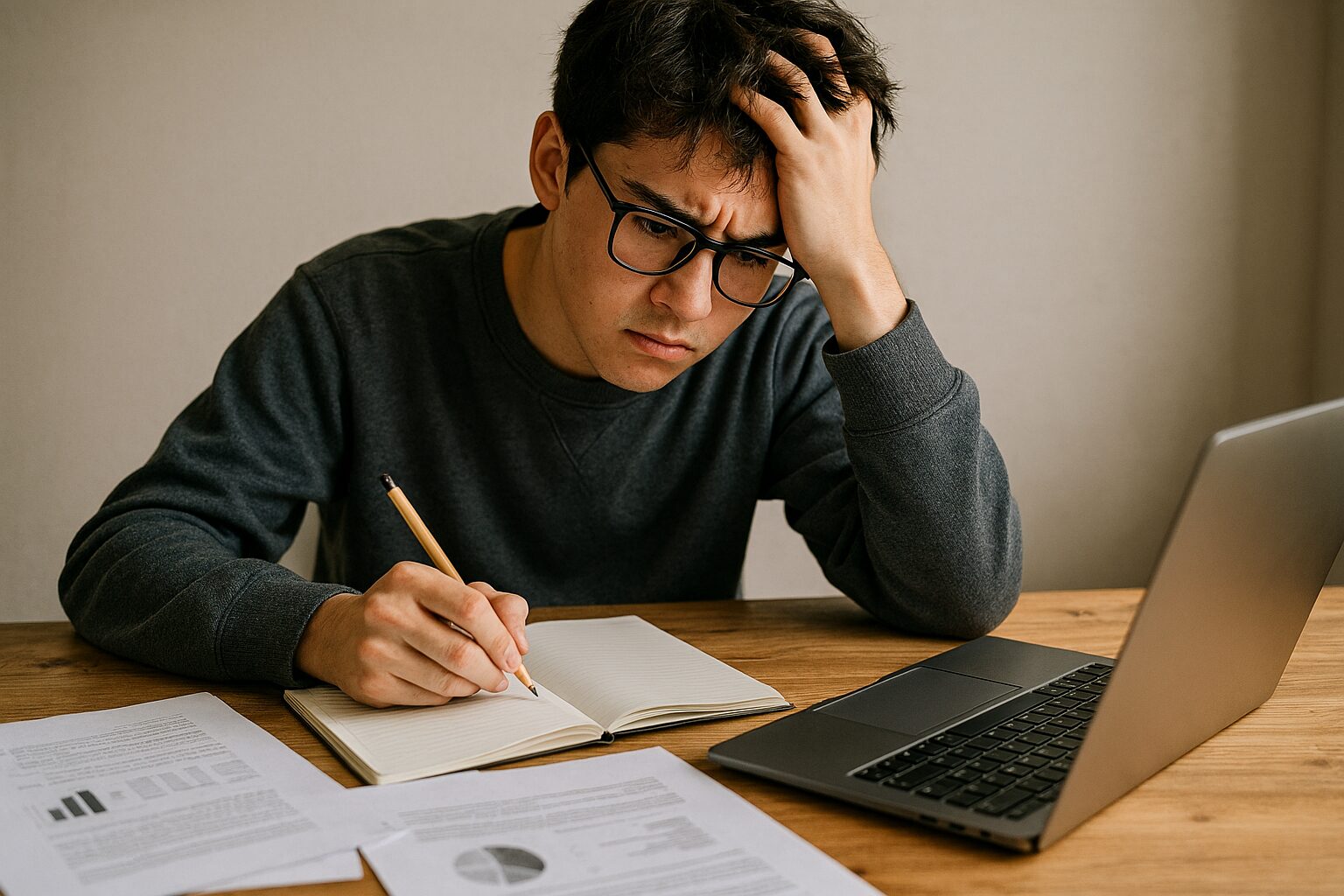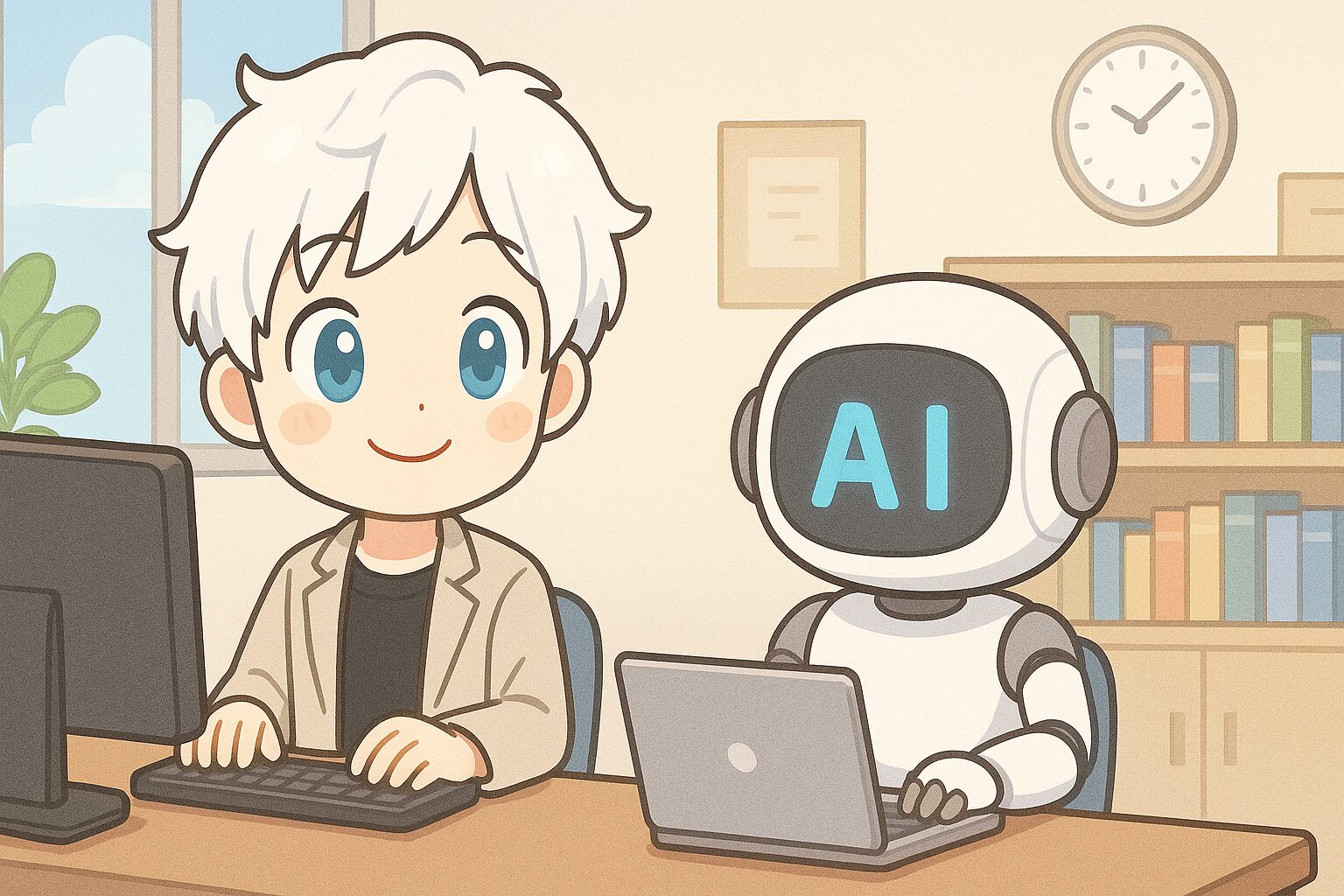博士課程(博士後期課程)必要な英語力は?
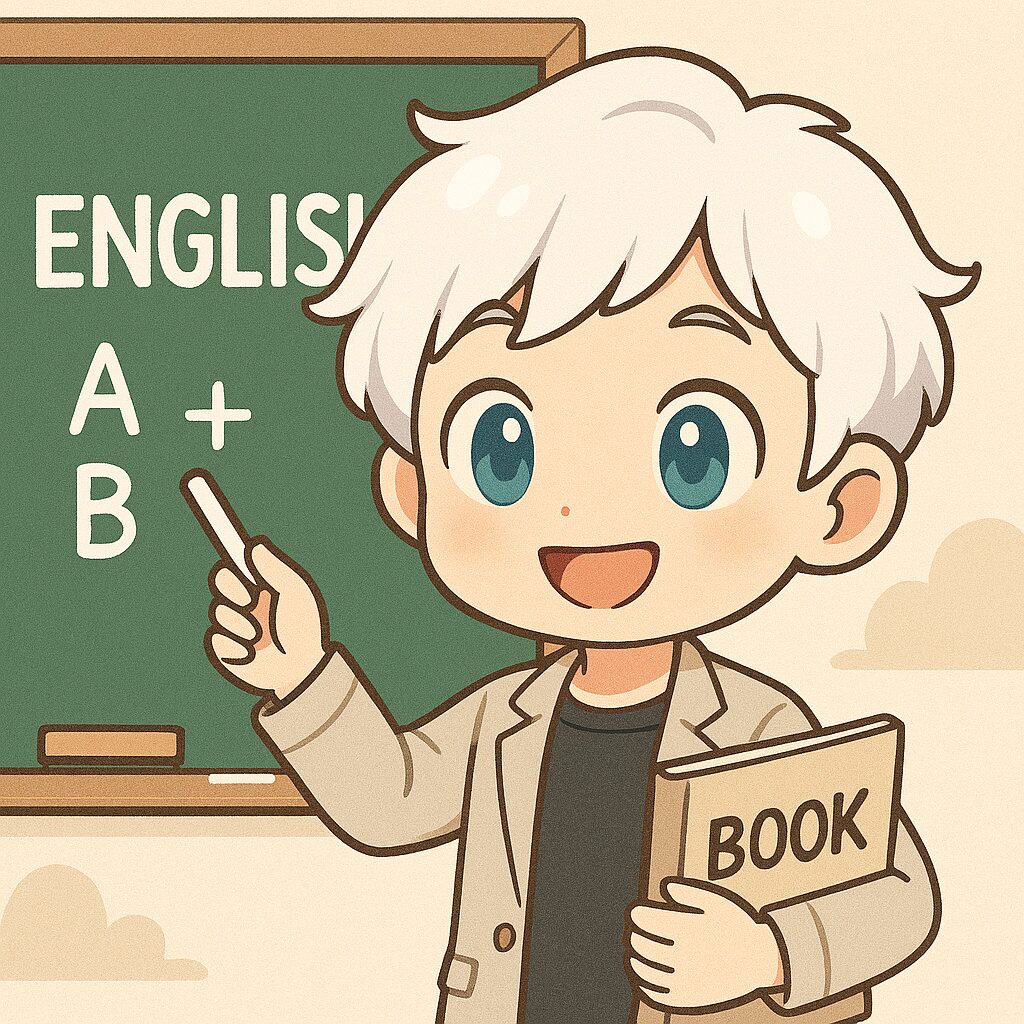
博士課程(修士課程(博士前期課程)後の課程になります)、いわゆる○○博士という資格、学位を取得するために通らなければならない道です。
海外での発表や論文を読み自分でも執筆する。
人にもよりますが、英語を使う機会は大量にあります。
では具体的にどれくらいの英語力が必要で、どのように身に着ければいいのでしょうか?
今日はそんな博士課程で必要になる英語力についてお話ししたいと思います。
結論
そんなに高い英語力はいりません。大切なのは…
博士課程 そもそも英語力が必要?
そもそもですが、博士課程では英語力が必要なのでしょうか?
分野にも依りますが、前提として研究とは
「誰もしらない未知のことを突き止め、それを社会へ還元する」行為です。
実学に近い研究分野は社会還元をより強く求められます。(例えば工学の航空力学など)
また、理学的な色が強い場合(自然界の原理原則を明らかにするなど)は世界中の誰も知り得ないことを誰よりも早く探求し、それを周知することが必要になります。
したがって、どちらのコンテキスト(文脈)においても世界(社会)へ還元することになります。
これは日本規模ではなく、日本の反対側にあるブラジルでも、もちろんアメリカや中国、イギリスやフランス、インドやオーストラリアでもおこなわれているものです。
研究者は世界中にいて、日夜実験、フィールドワークなどの活動に励んでいます。
そうなると、どうでしょう。自分が研究している分野、テーマの情報を日本語の資料だけで集めていては圧倒的に足りません。
常に競争。ドッペルゲンガーの如く。
今この瞬間にも、同じテーマの研究で、世界のどこかにいる5人の人間が成果をあげるために競争しているものと認識してください。
そうであるならば必然、人口が多い国の言語、世界的に標準として使われている言語で発信します。過去を振り返ると、やはりそれは英語です。
インターネット上には、英語のドキュメント、資料、論文があふれかえっています。
博士課程で研究をするならば、競争相手から情報を得たり、逆に自分自身の持つ情報を共有するためにも英語というスキルは必須になっています。
本当に必須?このAI時代に?
疑問を持たれることはわかります。
翻訳機能なんてかなり高度に発展していますし、英文をGoogle翻訳やDeepLに投げてしまえば分かり易く解説してくれます。
こうなればもう、英語力はそんなに必要ないのでは?と感じますね。
しかし、研究者同士での学会やオンラインミーティングで会話することをイメージしてみてください。
どうでしょう?翻訳ツールに向けて話してください。とだけ言えばいいのかもしません。
しかしコミュニケーションにおいて、このようにツールを使って翻訳して、反対に自分の言葉を翻訳してもらってそれを伝えるというプロセスは、ひどくストレスがかかります。
海外の人に道を教えるくらいなら、これくらいの負荷はなんともありませんが、学会などになると話になりません。
ですのでこの時代にあっても、最低限の英語力は必要になります。
実際の英語力の目安
じゃあ最低限の英語力って、具体的にどれくらい?
そうですね。
結論から先にお伝えすると、中学生から高校生くらいの会話力があれば問題ないです。
ただしそれは会話力、文法などの基礎的な箇所は、ということに注意してください。
なぜかというと、当たり前ではあるのですが、専門用語は中学校や高校では習わないからです。
それはそうですよね。いきなり授業で”supernova explosion”(超新星爆発:惑星科学などで使いますね)や”Hippocampus”(海馬:医学や生物学で使います)と習っても使いどころありませんから。
なのでSVO、SVOC、SVCなどの本当に基礎的な文法や会話の仕方を知り、実践できれば、あとは専門用語を適宜学んでいけば大丈夫です。
大切なのは…
中学生から高校生レベルの英語力を身に着けることからスタートを切れますが、そこからの英語力はそこまで高いレベル(ネイティブレベルなど)は本当に必要ありません。
そこからは何より「伝わる」ことが大事です。
つまり誠実に、分かりやすく伝えることを常に心がけましょう。
変に難しい文法にチャレンジしたり、難しい単語を使ってしまうと全然伝わらなくなってしまうことがあります。
これは英語圏における生きた(普段から使われているという意味合いでの)英語とギャップがあるからです。こればかりは、例えば留学などをすればよいのかもしれませんが、経済的にも精神的にもハードルは高いものですよね。
なので、生きた英語を真似することはいいかもしれませんが、完璧には難しいので複雑なことは考えず、
「誠実に、分かりやすく伝える」ことを頭の片隅に置いておきましょう。
じゃあどうやって学べばいいの?
もし中学生~高校生レベルの英語力が身についてないのであれば、教科書を引っ張り出してきて読み直してもいいですし、今はDuoLingoなどのアプリケーションも充実しています。無料でもかなりいいレベルまで押し上げてくれるでしょう。
そこから進んで、専門用語を使えるようになるにはどうすればいいか。
これは非常にシンプルです。
論文を読みましょう。英語の専門書を読みましょう。
いや、いやいやいや…
それができないから困っているし、学習の仕方を聞いているんですよ、との声が聞こえてきます。
そうですよね…私もそう思います。
ただ、色々な方法を試したり、人に聴いたりした結果、自分の中でもこの結論にいたりました。
読めなくてもいいから、一日一段落でもいいから、論文を読解してみる。
精読する、といってもいいでしょう。
丁寧に、古代文字を探求する学者のように、一単語一単語ずつ分解して解釈して、時間をかけてもいいから読みましょう。
そうすると、次第にあなたの脳に専門用語が自然と定着します。5本読み終えるころにはかなりの量の専門用語がインプットできるはずです。
私は最初、二ページしかないのに英語の専門誌の文章を読むのに1週間~2週間かけました。
全然わからないから、知らない単語がでてくるたびに検索して意味を調べてを、淡々と続けていました。
この作業ばかりは、愚直に回数を重ねていくしかないと思います。
厳しい現実を突きつけるようですが、これが本当に最短コースになります。
おわりに。
簡単にいけばいいのですが、そうもいかないのが専門性の高い領域です。
この記事を読んでいるということは、なんとなく博士課程に興味があるけど英語できないしなぁ、あまり自分の英語力に自信がないな、と思っている方かもしれません。
博士課程にチャレンジしようという心意気は天晴れなものですし、過去に私が通った道でもあります。
是非チャレンジして欲しいのと同時に、英語力は毎日の積み重ね、継続がかなり響くものです。
毎日少しずつでもいいので、精読してみましょう。
気付いた時には、かなりスムーズに、一日1本や3本の論文をすらすらと読めるようになっているはずです。
どれくらいの時間がかかるかは分かりませんが、確実に博士課程で通用する英語力を身に着けたいと望むならば、愚直に積み重ねましょう。
今日も一日、少しでも積み重ねられたら、素晴らしい!
どうか素敵な研究ライフを目指して、トライ&エラーで頑張りましょう!
それでは、また。